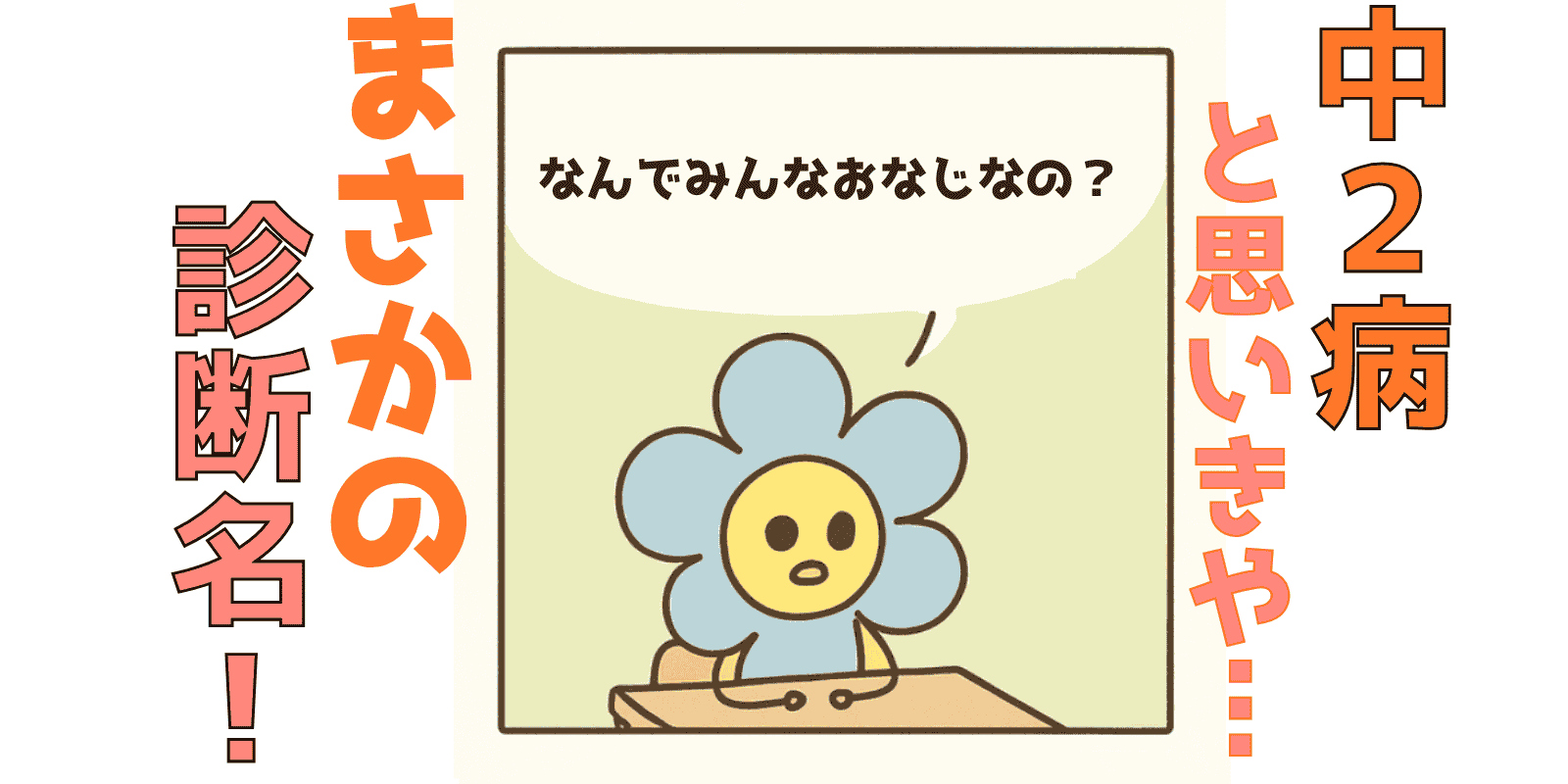繊細な次男くんが、学校に行けなくなった日
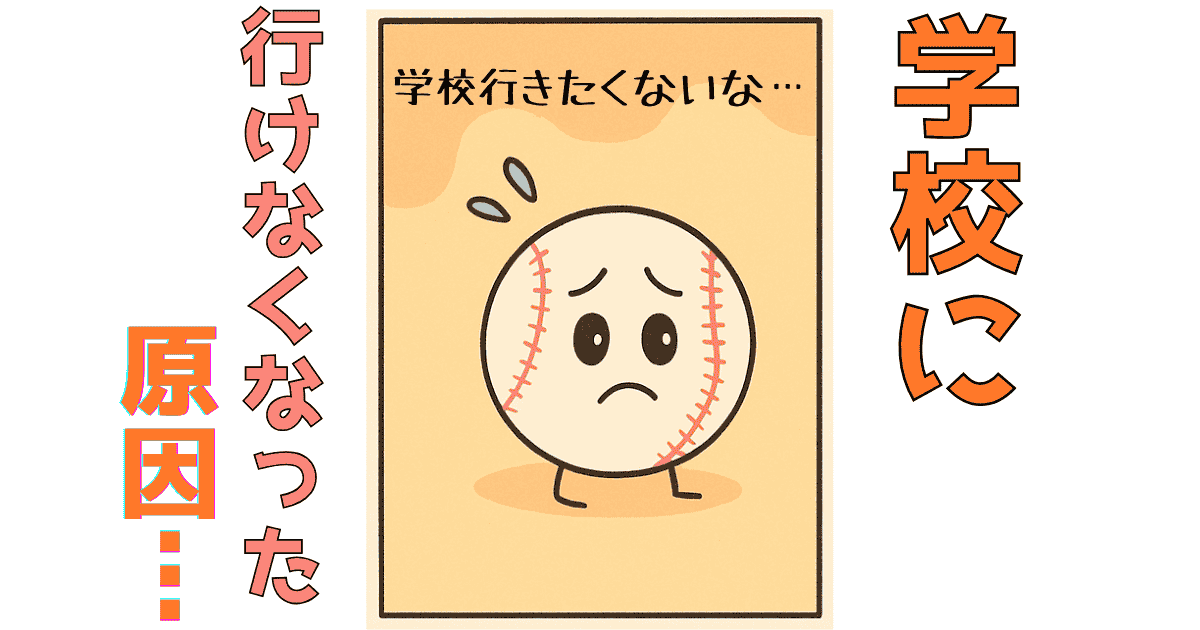
― 担任からのひと言が、心を閉ざすきっかけに ―
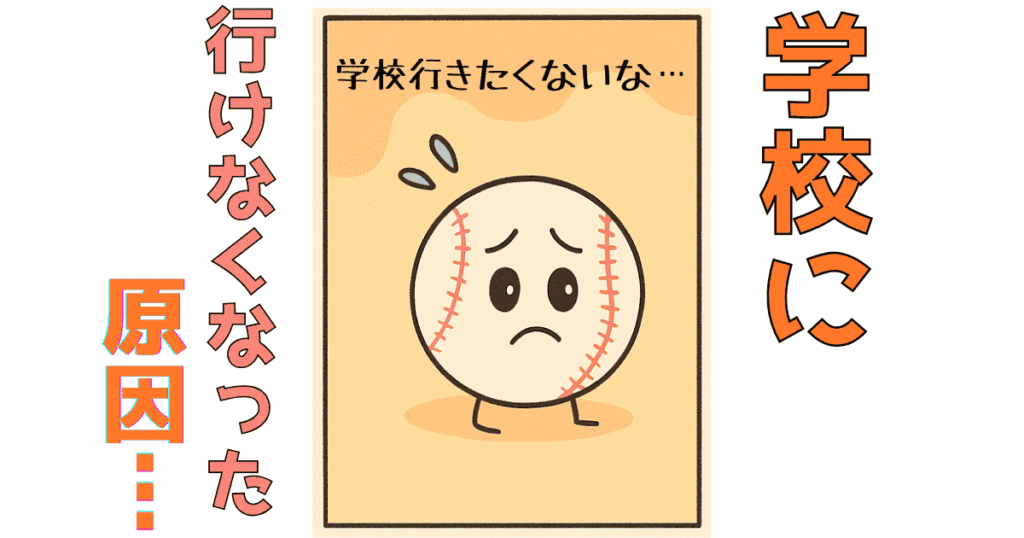
次男くんの不登校になった体験談
わが家の次男くんは、小さな頃からとても繊細な子でした。
武道と野球を両立し、頑張り屋さんな一方で、ちょっとした一言でお腹が痛くなったり、時には過呼吸を起こすこともあるような、感受性の強い子。
中学校に上がって2学期ころ、「おなか痛い」とたまにある休みたい病の言葉が…
◆不登校のはじまりは、担任との関係から
次男くんの担任は、生徒に対してとてもフレンドリーな態度と、理不尽にヒステリックに怒鳴ることもあるような情緒不安定…な先生でした。
親の前では別人のように穏やかに振る舞うので、子どもたちは「本音を言っても無駄」と感じていたようです。
そんな中、次男くんは学校に行くのが嫌になり、ある日とうとう不登校になってしまいました。
◆決定打となった“スクールカウンセラーでの出来事”
実は、不登校の決定的なきっかけとなったのは――
スクールカウンセラーとのやり取りでした。
ある日、担任の先生から「午後にスクールカウンセラーの予約がある」と次男に伝えられていました。
私(母)にも「午後からでお願いします」と聞いていたのに、当日の午前中、私へ怒り気味の電話がかかってきました。
「お子さんがまだ来ていません!
カウンセラーの先生の時間が空いてしまいました!」
後で聞くと、担任の伝達ミスだったのですが――
私は、自宅にいた次男くんに連絡を取り、とにかくカウンセラーの先生と話したら帰っていいから、学校へ行くようと伝えました。
カウンセラーの教室へ行く際、担任の先生とすれ違い挨拶をすると、
「睨まれて無視された」
と、帰宅した私へ伝えてく出ました。
まるで「時間を守らなかったあなたのせいで迷惑がかかったのだ」と言われたように感じた次男くん。
繊細な彼の心は、その態度で完全に折れてしまいました。
◆親として、次男くんにかけた言葉
「嫌な気分になったね…。先生も人間だから、きっと嫌なことがあったのかもしれない。でも、生徒にそのまま感情をぶつけるのは違うよね。」
担任の先生からの対応で心が疲れていた次男くんに、私はそう声をかけました。
「でもね、その態度を見て“自分はこうはならないようにしよう”って学べたら、それだけで意味があると思うよ。」
そして続けました。
「小さな学校っていう場所は、大きな社会に出る前の練習の場なんだよ。嫌な人との関わり方や、心の距離のとり方を学ぶために学校に行くの。勉強だって、知りたい!こうなりたい!って思ったときに、どうやって調べていくかを知っていれば大丈夫。」
「だから、学校に行くことは、テストの点だけじゃない。生き方のヒントを探す場所でもあるんだよ。」
「時間を間違えたのは先生だけど、カウンセリングは受けてほしかったから、無理にいかせてごめんね。」
次男くんが少しでも心を軽くできるように、そんな思いを込めて伝えました。
◆学校との話し合いで“別室登校”へ
その後、私たちはすぐに学校と面談をしました。
教頭先生は、「担任に原因があることは把握しているが、年度途中での交代は難しい」とのことで、
次男くんが担任と極力関わらなくて済むよう、別室登校という形が提案されました。
授業は担任以外の教科に参加し、ホームルームや給食は別室で。
ただ、繊細な次男くんにとって、先生に対して不信感を抱いたまま登校するのは簡単なことではありませんでした。
◆友達の存在と、“見守られながら”の回復
次男くんは友達に恵まれていたことも救いでした。
給食の時間には、クラスの子たちが「給食持ってきたよ!」と別室に喜んで運んできてくれました。
かわるがわるいろいろな友達が、気にかけてもらっていることが伝わり、少しずつ「友達に会いに学校に行こう」と感じ始めるように。
翌年度、担任の先生が学校を離れたことで、次男くんは通常登校へと戻っていきました。
◆もともと小学生のころから見えていた“繊細さ”
実は、小学生のころから、繊細なサインは現れていました。
多汗症のことをからかわれ、「臭い」と冗談で言われたことに深く傷つき、数日休んだことも。
大事にしていた野球のグローブを勝手に使われ、それでいつものプレイが出来ず、悔しさと怒りでいっぱいになったこともありました。
こうした「こだわり」や「感覚の敏感さ」は、本人にとって大切な“自分らしさ”でもあるのです。
【まとめ】
「不登校」という言葉には、まだまだネガティブなイメージがつきものですが、
それはわがままでも、甘えでもない。
繊細な子にとって、「信じていた人からの何気ない一言」が心に深く突き刺さることがあります。
学校や先生との“相性”が悪かっただけで、本人の性格や能力に問題があるわけではありません。
次男くんも、支えてくれた家族や友達のおかげで前を向き、前へと進んでいけました。
)-150x150.jpg)